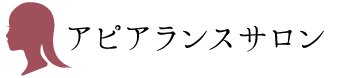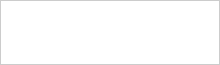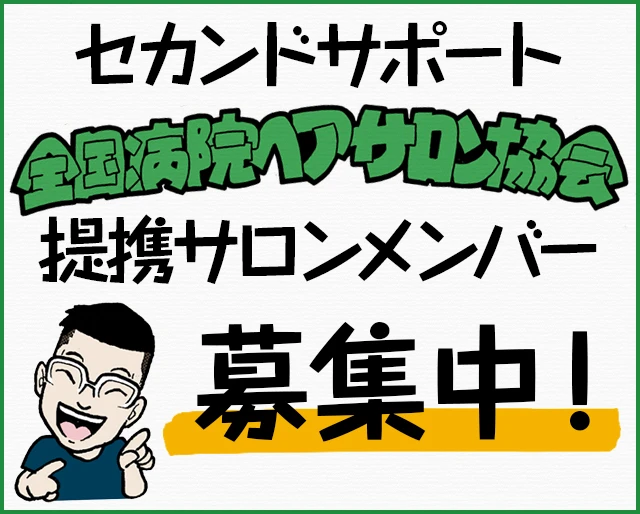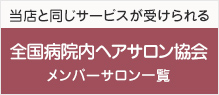がん治療中および治療後の運動の効果では、「運動によるリハビリテーション医療と栄養管理が、全身衰弱や筋肉の萎縮・筋力低下を防ぐうえで最も重要」とされています。
また、「運動は身体機能を高め、疲れにくくし、精神的苦痛を軽減して生活の質(QOL)を向上させる」ことが示されています。
以下に、その内容をもとに一般論も加えて整理します。
1. 身体的な効果
● 筋力・体力の維持
抗がん剤や放射線治療中は、倦怠感や食欲不振などから活動量が減り、筋肉量が急速に落ちやすくなります。
運動によって筋肉への刺激を保つことで、
- 筋萎縮(サルコペニア)の予防
- 基礎代謝の維持
- 日常生活動作(ADL)の改善
につながります。
特に「週150分以上の中等度の有酸素運動」と「週2〜3回の筋力トレーニング」が理想的とされており、この組み合わせは疲れにくい身体づくりにも有効です。
2. 疲労感(キャンサー・リレーテッド・ファティーグ)の軽減
多くの患者さんが訴える慢性的なだるさ(倦怠感)は、安静よりも適度な運動で改善することが科学的に確認されています。
軽いウォーキングやストレッチでも血流改善と酸素供給促進につながり、
- 睡眠の質向上
- 食欲増進
- 活動意欲回復
など複合的な好循環を生みます。
3. 治療成績への良い影響
近年では、「治療中から安全に行う適度な運動」が免疫機能や炎症反応にも良い影響を与えることが報告されています。
また、大腸がんなど一部の疾患では、「定期的な運動習慣」が再発予防にも関連すると考えられています。
これは、インスリン抵抗性や慢性炎症マーカー(CRPなど)の改善、およびホルモンバランス正常化によるものと推測されています。
4. 精神面への効果
専門家による知識体系でも強調されているように、「運動は気分転換になり、精神的苦痛を和らげる」作用があります。
実際、有酸素運動には脳内でセロトニンやエンドルフィンといった“幸福ホルモン”を増加させる働きがあります。その結果:
- 不安・抑うつ症状の緩和
- 自己効力感(自信)の回復
- ストレス耐性向上
これらは治療継続への意欲にも直結します。
5. 社会生活への復帰支援
体調回復後も継続して運動習慣を持つことで、
- 職場復帰時の体力不足解消
- 日常生活範囲拡大(買い物・外出など)
- 再発予防および生活習慣病対策
といった長期的メリットがあります。「徐々に行動範囲を広げて日常生活へ戻っていく」こと自体がリハビリテーションとして非常に重要です。
6. 注意点 ― 「無理せず継続」
ただし、副作用や体調変化には個人差があります。
- 発熱・強い倦怠感・貧血時は休む。
- 抗がん剤投与直後など免疫低下期は人混みでの活動を避ける。
- 運動内容は主治医またはリハビリスタッフへ相談して決める。
「頑張りすぎない」「少しずつ続ける」が成功の鍵です。
まとめ
運動には、
「身体機能維持」「疲労軽減」「精神安定」「再発予防」
という4つの柱となる効果があります。
つまり、適切な運動とは単なる“体操”ではなく、“治療そのものを支える医療行為”です。
無理なく楽しめる範囲から始め、自分自身のペースで継続することこそが、心身両面で最も大きな成果につながります。