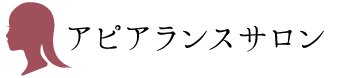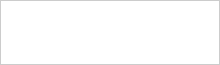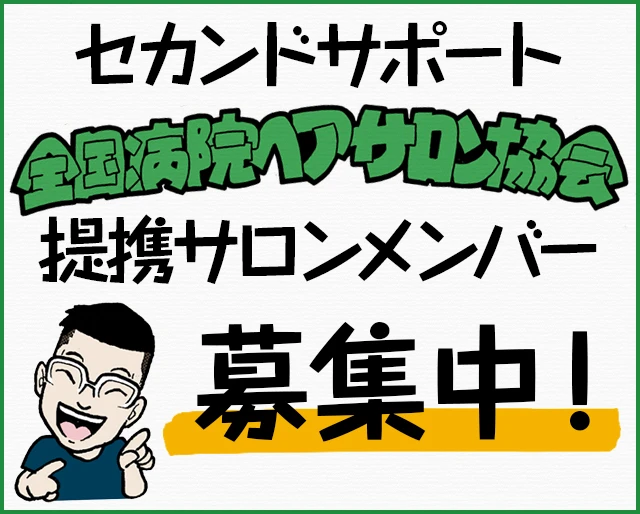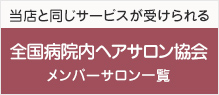抗がん剤治療や脱毛症などで医療用ウィッグ(かつら)を利用している方にとって、「かゆみ」は非常に多い悩みのひとつです。
せっかく自分らしい外見を保てるアイテムでも、頭皮がムズムズしたり、我慢できないほどの不快感が続くと、日常生活そのものがストレスになりかねません。
「どうしてこんなにかゆいの?」「何か良い対策はある?」――そんな疑問や不安を抱えている方へ。
一般的な工夫例をもとに、「医療用ウィッグ着用時のかゆみ」の原因と具体的な対策について詳しくご紹介します。
1. 医療用ウィッグ着用時の「かゆみ」…主な原因とは?
(1)汗・皮脂・蒸れ
ウィッグは頭皮全体を覆うため、どうしても通気性が悪くなり、汗や皮脂がたまりやすい状態になります。
特に夏場や運動後は頭皮が蒸れてしまい、それが刺激となって「ムズムズ」「チクチク」とした不快感につながります。
(2)乾燥・摩擦
抗がん剤治療中は頭皮自体もデリケートになりやすく、乾燥しやすい傾向があります。
また、ウィッグ本体やインナーキャップとの摩擦によって肌表面が刺激されることで、かゆみを感じることも少なくありません。
(3)洗浄不足・雑菌繁殖
ウィッグやインナーキャップのお手入れ不足で汚れや雑菌が増えると、それ自体が刺激となり頭皮トラブル(炎症・湿疹など)→さらに強い痒みに発展する場合があります。
(4)素材アレルギー
まれですが、ウィッグ本体やインナーキャップ素材へのアレルギー反応で赤み・発疹・強い痒みなどを生じるケースもあります。
「新品なのに急に痒くなった」という場合は素材にも注意しましょう。
2. 具体的な対策ポイント
【A】清潔第一!こまめなお手入れ
- ウィッグ本体
使用頻度にもよりますが週1~2回程度シャンプー&陰干しがおすすめです(製品説明書記載方法厳守)。汗ばむ季節はもう少し頻度アップでもOK。 - インナーキャップ
毎日交換&洗濯しましょう。吸汗速乾タイプだとより快適です。 - 頭皮ケア
優しく洗浄し、汗拭きシート等でこまめにふき取る習慣も大切です。お風呂上りには低刺激ローション等で保湿すると乾燥予防にも役立ちます。
【B】通気性アップ&吸汗工夫
- メッシュタイプなど通気性重視のウィッグ選び
最近では夏向け商品も多く登場しています。軽量設計&髪量控えめタイプなら熱こもり感も減ります。 - 吸汗速乾素材のインナーキャップ活用
スポーツウェアにも使われるような薄手タイプがおすすめです。 - “換気タイム”確保
自宅ではできるだけ外して頭皮を休ませましょう。一人になれる空間=解放タイム、と割り切ってください。
【C】摩擦軽減
- サイズ調整で締め付け過ぎないよう注意
キツすぎるとかえって摩擦増加→痒み悪化につながります。 - 縫い目少なく肌当たり柔らかなもの選び
インナーキャップ選びでも重要ポイントです。
【D】異常時は早め相談!
- 赤み・発疹・強い痒みなど異常症状出現時は我慢せず主治医または看護師へ相談しましょう。
- 素材変更(別メーカー品試用等)も検討可能です。「こんなの聞いていい?」と思わず遠慮なく伝えてくださいね。
3. 季節ごとの工夫&便利グッズ活用
夏場は特に「冷却グッズ」もうまく取り入れてください。首元保冷タオル、小型扇風機(ハンディファン)、UVカット帽子併用など熱中症予防にも役立ちます。
また冬場でも暖房による乾燥から痒みに繋がることがありますので室内加湿器利用もおすすめです。
4. 気分転換&サポート活用
どうしてもしんどい日は無理せず休む勇気も大切です。
また病院内アピアランス支援窓口では、新しい商品情報や他患者さんから聞いたアイデアなど有益情報が得られる場合があります。
「一人じゃない」と思えること自体、大きな安心材料になるでしょう。
同じ経験者同士の交流会(ピアサポート)参加で安心感につながったという声も多いです。
5. 家族・周囲とのコミュニケーション
家族としてサポートする側の場合、「何とか元気になってほしい」と思うあまり無理強いや励まし過ぎになってしまうケースがあります。
「今日はこれしか無理だった」「今はこういうものしか受け付けない」と本人から伝えてもらうことで理解されやすくなるため、自身の状態について率直に話すことも大切です。
また、お子さんの場合には年齢相応に説明した上で一緒に帽子選びなど“楽しいイベント”として取り組む工夫がおすすめです。
【まとめ】
医療用ウィッグ着用時の「かゆみ」は、多くの場合「蒸れ」「乾燥」「摩擦」「お手入れ不足」など複数要因が絡んでいます。
基本は「清潔」「通気性」「保湿」の三本柱。
そして困った時には遠慮なく病院スタッフや専門店へ相談しましょう。
「一人で悩まずまず相談」“あなた自身”が少しでも楽になれる工夫、ご自身ペースで見つけてくださいね!